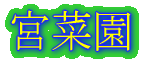
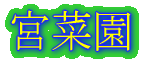 |
接木-宮式高接 | TOP PAGE 菜園インデックス 果物 山菜 野菜 |
| 接木事例(キウイ、桃、柑橘類等) 葡萄の接木 桜の頃の状態 実が太る頃の状態 次年度早春の状態 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
宮式高接方式 書籍などで記載されている幾つかの高接ぎを試して見ましたが、思った様に接木の成功率が上がりません。そこで自分なりに工夫し試行錯誤した結果を勝手に宮式高接方法としてまとめてみました。 方式に関する注意、補足説明 接木に習熟されている専門家の方からみると、単なる従来から行われている手法の延長であり、特に目新しい方法ではないのに、勝手に名称を付けており、しかもあたかも他の方法より成功率が高いように記載されているのはおかしいと感じる方が多いかも知れません。又従来の方法で成功率が上がらなかったが、本方式で成功率が上がった様に記載されているのはおかしいと思われるかも知れません。多分、他の方式に習熟されている方からみるとそうだと思います。筆者が他の方法で成功しなかったのにこの方法で成功するようになったのは、あくまでも、あまり接木が得意でない時点で始めたのがこの方法であり、この方法が比較的スムースに導入・実施出来たとお考え頂けたらと思います。 何からかの方法が好まれる要素は色々あり、確実性(接木では成功率でしょうか)、容易さ(これは個人の器用さにより変ってきます)、範囲(接木では色々な木種に適用可能となるでしょうか)、それにその方法を容易に習熟できる資料の有無、等が考えられます。 名称はあくまでも説明上付与したものですので、あまり名称にはこだわらず、接木事例などを見ながら気楽に実施してみて頂き、成功するようになったら自分なりの工夫を加えて頂ければ良いのではないかと思います。 特長 穂木と同じ位の太さの枝からかなり太い枝にも接木可能。(ただし、最良なのは台木より穂木が少し細い位のもの) 自由な位置に複数箇所の接木が可能。 作業が容易。(高度な熟練が無くても成功率が高いと言った方が良いかもしれません) 方法
その他注意事項など ①台木の接木した部分より先の方の枝を残したままでも接木は可能ですが、接木した部分が良く生長するためには、穂木以外の新芽は掻き取った方が穂の成長は早い。 台木の接木した部分より先を残すのは、失敗した場合に再度接いだり別の品種を接ぐ等の単純な理由の他、木の種類によっては枝を長く残すことにより負け枝になる事を防ぐ目的もあります。原則として残した枝の芽は早めに全部掻きとりますが、穂木から出た芽のほかに先端の方から出た台木の芽も少し残した方が、接いだ枝の枯れこみの可能性がなくなると同時に、穂木の成長も早い事が多い様です。私の場合、接いだ先は最低20cm程度、場合によっては50cm位残しておき、接ぎ穂の支柱に利用します。又、台木の芽は全部掻き取ると説明しましたが、掻き取っても又芽が出てきますので、そのうちの一部は少し残し、台木が完全に枯れない様にしています。2年程して穂木の方が太くなってから台木を剪定するのが理想的な様です。 ②穂木は台木より少し細め位が、形成層を合わせやすく、テープでの乾燥防止の密閉が容易。 ③古い枝は皮が厚いので形成層の位置に注意が必要 ④カットした穂木の長さが、台木の切り込みよりわずかに短い位にすると、穂木を取りつけたとき密着し易く、そのままにしておいても脱落しないので、テープを巻くとき用意であり位置ずれ等が起きにくい ⑤通常は芽だけ出す様にするが、特に乾燥防止をしっかり行い成功率を上げたい場合、芽の部分もテープで覆う事も可能です。この場合芽が動き出してきたら少し切り込みをいれる手間が必要になる。 ⑥穂木を半分に割った後、カンナで削る様に軽く削り平らにすると成功率が上がる様ですが、細い穂木の場合テープで強く縛ることにより、多少よじれなどがあっても活着する事が多い様です。 ⑦テープは広げた状態で巻き気密性を保持する様にするが、最後はテープを丸め気味にして芽の上下を強く縛る様にすると密着性が高まる ⑧接木した果物の種類は接木テープに直接油性のサインペンで記入してもしばらくは大丈夫ですが、確実に長期間記録を残す為には、ビニールテープに品名を記入し、巻きつけておいた方が安全です。 ⑨穂木の保存は、密封性の高いポリ袋等に湿った布や水苔等と共に入れ、冷蔵庫で保管します。ポリ袋は破れ易いので、ポリ袋をさらにビニール袋に入れ2重にして保存すると安全です。柿では適度な湿度を保つことにより、一年以上保存した経験もありますが、水分が多すぎると黒カビ等が発生し、穂木の内部まで黒く変色し穂木が腐食することがありますので、長期間保存する場合、穂木をポリ袋に入れ、外側に湿った布等を入れ、全体をビニール袋に入れるのが良いでしょう。 穂木は乾燥して干からびてしまうのが最悪ですが、水が滴るほどの過湿も芽や幹自体の腐敗の原因になりますので注意が必要です。 2018年1月21日更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP PAGE 菜園インデックス 果物 山菜 野菜 |