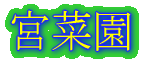 |
カマキリ | TOP PAGE 菜園インデックス 菜園小動物 作業記録 果物 山菜 野菜 |
カマキリについて カマキリは毛虫やチョウ、ハエ、コオロギ/バッタ類、油虫等を食べてくれるので菜園の大切な小動物です。以前は、大量に発生していたバッタ類も細々と生息するだけになり、ケムシの親である蝶々や蛾の数もだいぶ減って来た様に感じられます。害虫が全滅という訳ではないですが、果物や野菜の被害があまり気にならない程度に減って来たケースが増えています。 2004年3月にカマキリの卵を数えて見たのですが、スモモ2ヶ所、山椒、ウコギ、ビワ、プルーンに各1ヶ所づつ産みつけてありました。これまでは菜園全体で1〜2ヶ所程度だったので、随分増えたものです。ただ、これ以上増えるかどうかはカマキリの食料事情によりそうです。一つの木に3ヶ所以上卵を産みつけたのを見たことがありませんので、通常の大きさの木なら木一本が縄張りの範囲で、大人のカマキリはそれ以上は食料の関係で生息出来ないのかも知れません。 尚、食料の他にカマキリが増えるのを抑える昆虫がいることも判りました。5月になっても孵化せず卵の塊の一部に穴が空いている場合、カマキリタマゴカツオブシムシという昆虫にタマゴを生みつけられている事があります。親は数ミリのコガネムシを小型にしたようなムシであり、秋にカマキリの卵塊の中に沢山の卵を産みつけます。この昆虫の卵が孵化すると蛆虫を茶色にしたような2、3mmの幼虫となり、冬の間にカマキリの卵をどんどん食べて大きくなりますカマキリの卵を食べ尽くすころには脱皮して飛び立っていく様です。 このカツオブシ虫は、カマキリの幼虫がいなくても卵塊のなかで育つようなので、カマキリが付加した後には、卵塊を回収し発生を抑えるようにしています。 カマキリの生息数の状態等 2004年 − カツオブシ虫によりほぼ全滅状態 2004年5月に4個のカマキリの卵塊を確認したときは以下の様になっていました。 ①孵化寸前のカマキリが数匹残って動いている状態であり、カツオブシムシの幼虫も生きている状態。 ②カマキリの卵は食い尽くされた状態であり、カツオブシムシは脱皮した抜け殻のみ残っている状態。 ③カマキリの卵は食い尽くされた状態であり、カツオブシムシの小さ目の幼虫が干からびて死んだものが大半の状態。 ④卵塊は小さめだがカツオブシムシの被害は見当たらない状態。 2004年はどうやら④の卵も孵らず菜園にカマキリの子供が全く見当たりませんでしたが、住宅側の庭木の中に沢山の子供が見つかった事から、40匹ほど捕獲し菜園の数ヶ所に放牧(?)しました。 2005年 − 生息数が少し回復 2004年春に放牧したカマキリが何匹か生き残ったとみえて、秋に菜園の手入れ中に10個ほど卵塊が見つかり保管しました。 2005年春に、菜園に戻したところ順調に孵化し、秋には10数個の卵が産み付けられていました。 2007年 − 一気に卵を増やして、生息数の飽和を調査 菜園で活動出来るカマキリの数とカツオブシムシの被害の程度を調べる為、散歩の途中等で見つけた卵を30個程集め、菜園で採取した卵と合わせ43個の卵塊を得られました。これらを5個づつ小枝に固定し、ウコギ、葡萄、モモ、梨、ミカン、スモモ、ビワ、キュウイ等の枝に吊るしました。これで多分菜園はカマキリが飽和状態になると思いますので、害虫の発生状況、秋の卵の数、孵化した割合、孵化の時期にカツオブシムシに食われている割合等を観察・記録してみました。 卵の回収と状況確認の結果(同年初夏ごろ実施)、以下の様な結果と成り、ひとまず回収は有効と判断出来ました。 ①孵化が完了しカツオブシ虫の食害もなかったもの 27個 ②カツオブシムシに食べられていたもの(多分春先) 6個 ③カツオブシムシの幼虫がいたもの(孵化は成功) 9個 (多分②の成虫が今年産みつけたもので、まだ小さなカツオブシムシの幼虫が生息) 2008年 − 生息数の確認 7月初旬にカマキリの孵化は完了したと判断し、卵塊を収集し確認しました。卵塊を開いて見たらカツオブシムシの被害状況は以下の様になっていました。 ①カツオブシ虫の被害が無いもの − 8個 ②カツオブシムシの小さな幼虫がいたもの − 9個 ③カツオブシ虫の幼虫の抜け殻があったもの − 1個 (これは昨年既に食害されていたものと思われます) 確認した卵塊は全て焼却処分しましたが、カツオブシ虫に食害食害されている割合が依然高く、今後も春先のカツオブシムシ孵化前のチェック、7月ころの収集、チェック、焼却処分が必要と判断しています。尚、カツオブシ虫が新しい卵塊に卵を産み付けるのは秋ですが、秋に卵をが産み付けられているかどうかはなかなか難しい様で、今のところ産み付けられているかどうかの見分けは出来ていません。幸い秋に産み付けられてカマキリの卵/幼虫が食べられているケースは少なくなって来ていますので(2008年では③のケースが秋に産み付けられた可能性がある)、カマキリの孵化が完了する6月から7月頃に卵塊を回収すれば、春先に産み付けられたカツオブシムシの幼虫が孵化する前に駆除でき、その後の繁殖に必要なカツオブシムシの食料を絶つ事も出来ると思っています。 尚、2007年に一気に卵塊を40個程に増やしてみましたが、2008年ではまた20個弱に減ってきていますので、宮菜園では10個〜20個位が自然な数の様です。 まとめ これまでの観察記録等から、概ね以下の対応を行なう事としました。 * 全体の8割位は一旦卵塊を回収する。 * 4月頃に数個ずつまとめ、回収し易いわかり易い場所に卵をつるしておく * 5月〜6月ころカマキリ孵化を確認・取り除き(このころカツオブシムシも孵化) * 7月ころ卵塊を全て回収して棄却(カツオブシムシの産卵は6月頃から8月中旬頃)
2015年3月13日更新 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP PAGE 菜園インデックス 菜園小動物 作業記録 果物 山菜 野菜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











