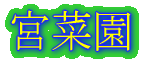
野菜作業記録 果物 山菜
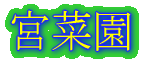 |
野菜の世話 | TOP PAGE 菜園インデックス 野菜概要 野菜作業記録 果物 山菜 |
野菜の世話について 野菜によってかわいがり方は異なります。肥料を沢山与えるとよくできる野菜もありますが、かえってだめなものもあります。日光を好む野菜/好まない野菜、植える時期が大変重要な野菜とそうでない野菜、寒さに弱い野菜/熱さに弱い野菜など色々です。 各野菜毎に注意の必要な点、面白い点等を記述して見ました。 尚、一般的な事は本屋さんで売っている菜園の本に書いてあるのでここではあまり紹介していません。 何冊か本を読んだ上であらためて感じた事や知った事を紹介させて頂いています。 苗作り ナス、トマト、接木キュウリ等植える数が少ないものは春に園芸店で購入しますが、その他の野菜は通常プランタやポットに種を播いて自分で苗を作ります。 特に、インゲン、枝豆、時期はずれのキュウリ、ブロッコリ等時期をずらして植えておくと長期間楽しめるものは自分で苗を作るようにしています。 苗を作ってから植えると畑が有効利用できるほか、良い苗ばかり選んで植えられるなどのメリットがあります。 プランターの利用 パセリ、三つ葉、子ネギ、モロヘイヤ、ワケギ等少しあれば間に合う野菜はプランターに植えています。必要なときちょっと利用できるのでとても便利ですが、毎日水かけが必要な点は少々厄介です。 肥料 化成肥料を与えることは殆どありませんが、野菜によってはたまにあまりに勢いが無い場合、少し粒上の化成肥料を散布します。 大半は拾ってきた落ち葉や近所で庭師が剪定した小枝や葉っぱを野菜の周りに広げておくだけです。畑の周りの山菜や果樹の剪定葉っぱも良い肥料になります。 この葉っぱが少しずつ腐食し、ミミズにより拡散されるの待ちます。 草取り 畝の上に葉っぱ等を大量に播くためあまり雑草は発生しませんが、葉っぱを掻き分けて出てきた雑草は少し大きくなってからはさみで根元から切ります。 こうすると、根もそのうち肥料になりますし、切った雑草もいずれは肥料になります。 一番のポイントは種が出来るまで雑草を大きくしないことです。又野菜によっては雑草が嫌いなものがありますので(ネギなど)、そのような野菜の畝に生えた雑草は小さいうちに早めに抜き取ってしまうことです。 耕作 一度畝を作成したらその後掘り起こす事はしませんが、たまに長芋等の様な根菜を植えた場合は収穫のついでに掘り起こし堆肥を混ぜて置きます。 根コブ病、根腐病(線虫類)の防止 トウモロコシは線虫防除の効果があるということで1ブロック全体に植える様にしています。(4年に1回) 又次の作物に移る間に少し間があくことがありますので(又は作物が大きくなる前にスペースが空いていますので)、この間マリーゴールド(根腐線虫退治用)や瘤取り草(根コブ線虫退治用)を植える様にしています。当然これらの草も最後は堆肥化します。 堆肥作り 秋には近くの公園などに行って落ち葉を集めてきます。強い風の吹いた後等は道路の脇などにも大量に落ち葉の吹き溜まりが出来ていますので、大きなごみ袋を持って出かけかき集めてきます。 菜園に2個のコンポストを置き、交互に台所の生ごみを入れるようにしています。一個がいっぱいになったらそれには生ごみを入れるのを止め自然に堆肥になるのを待ちます。片方が生ごみでいっぱいの成るころには他方のコンポストの生ごみは堆肥化していますので、それを野菜や果樹の樹勢が弱そうなところに肥料として与えます。コンポスト置き場種は、生ゴミ一台所の生ごみと落ち葉を交互に摘んでいくようにします。たまってきたら2、3度かき回すと堆肥らしきものができますので、時々野菜の周りに播くようにします。(年に1,2度) 庭木の剪定枝の利用 近所の家では、専門の庭師に頼み1年に2度位庭木の剪定を行います。剪定した小枝や葉っぱはどうするかというと大概市のゴミ焼却炉に持ち込んで焼却してもらうことになります。これは庭師にすれば、持ちこむだけで結構大変らしく、剪定した葉っぱをくださいと言えば喜んでおいていきます。 この剪定枝には小さな枝なんかも混じっているのでそのまま堆肥を作ろうと思うと腐食して堆肥化するまで結構時間がかかります。そこで我が家の菜園では通路や畝の間に敷いておき、自然に腐食するのを待ちます。ミミズの餌にもなるし、畑の乾燥防止や通路のぬかるみの防止にもなり結構重宝しています。 最初は自分の家の庭木だけだったのですが、最近では近所で庭木の剪定を行ったときも持って来てくれるようになりました。 |
TOP PAGE 菜園インデックス 野菜概要 野菜作業記録 果物 山菜 |